ヨガを始めると、たくさんのポーズとその名前が出てきますよね。日本語で言うこともあれば、サンスクリット語で呼ばれることも。私自身、ヨガ指導歴10年以上になりますが、正直、サンスクリット語でのポーズ名はほとんど覚えていません。昔は覚えていたものもありますが、使わないうちに忘れてしまいました笑
でも、日本語でのポーズ名はしっかり使います。なぜなら、それが一番「伝わる」からです。私のクラスに来る多くの方は、「体を整えたい」「不調を改善したい」「日常を快適に過ごしたい」という目的を持っています。だからこそ、僕はポーズの名前より、「何のための動きか」「どう動けば効果が得られるか」を明確に伝えることを大切にしています。
では、なぜ僕がサンスクリット語のポーズ名をあまり使わないのか、そしてそれがなぜ問題ないのか、これから詳しくお話ししていきますね。
サンスクリット語のポーズ名、本当に必要?
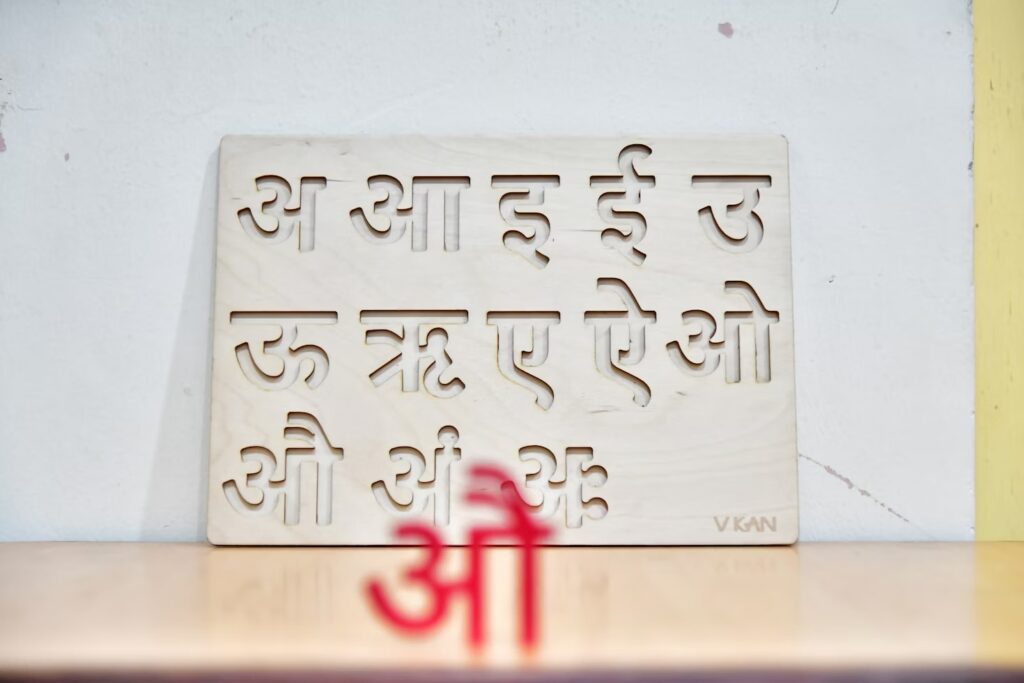
ヨガを学び始めると、たくさんのポーズ名にサンスクリット語が使われていることがわかります。カタカナで覚えるだけでも大変ですし、実際のレッスンでは、サンスクリット語を積極的に使う先生もいれば、全く使わない先生もいますよね。
僕自身、レッスンでサンスクリット語のポーズ名を使うことは基本的にありません。「戦士のポーズ」や「三角のポーズ」といった日本語のポーズ名です。なぜなら、僕のクラスに来てくださる方の多くは、「ヨガを探く知りたい」としてではなく、もっと身近な「身体や心を整える手段」として選んでいるからです。
そのような方に、いきなり「では、次はウッティタ・トリコナーサナです」と伝えても、何のことか分からず、かえってヨガへのハードルが高くなってしまうかもしれません。むしろ、「ヨガって難しいのかな…」と距離を感じさせてしまう可能性もあります。だからこそ、僕はあえてサンスクリット語をレッスン中に多用しないようにしています。
サンスクリット語を使わなくなった理由
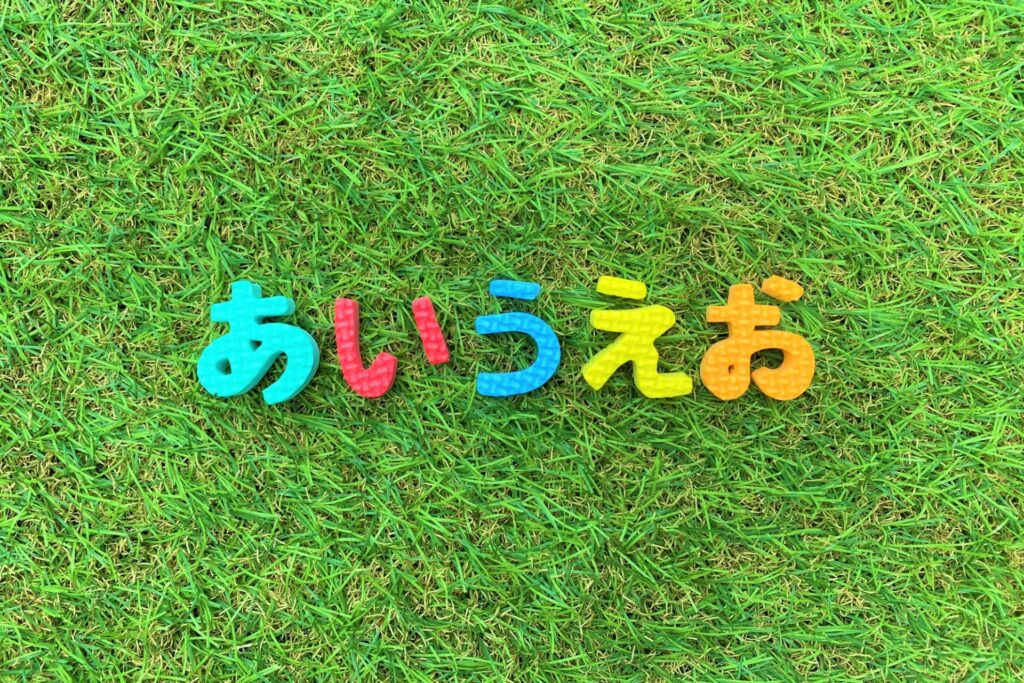
僕がサンスクリット語のポーズ名を使わなくなった理由は、一言で言えば「指導現場で必要とされないから」に尽きます。もちろん、ヨガを学ぶ過程では、ある程度のサンスクリット語の知識は身につけましたし、資格取得のための試験対策として頭に入れていた時期もありました。
しかし、実際に教える立場になってみると、サンスクリット語で話す機会はほとんどありませんでした。理由は明確で、参加者に伝わらないからです。
たとえば、「アルダ・マツェンドラーサナ」と言うよりも、「片膝を立てて、上体をひねるねじりのポーズです」と伝えた方が、圧倒的に理解されやすいのです。
僕のクラスには、運動経験が豊富な方ばかりではなく、「体が硬くて不安」という方や、「ヨガは初めて」という方も多くいらっしゃいます。そうした方々にとって、まず必要なのは、動きや意図が分かりやすい説明です。
また、サンスクリット語をあえて使うことで、無意識のうちに「ヨガは特別なもの」「自分には縁遠いもの」という距離を感じさせてしまうこともあります。
僕が目指しているのは、日常生活に役立つヨガ、誰もが健康的な身体づくりに取り組めるヨガです。だからこそ、必要以上に「ヨガの世界観」を演出するよりも、参加者の皆さんの生活に寄り添う言葉を選ぶようになったのです。
日本語での説明を軸にした伝え方

サンスクリット語を使わなくても、ヨガの素晴らしさや効果は十分に伝えることができます。私が日々のクラスで実践している工夫をいくつかご紹介します。
日本語のポーズ名を積極的に使う
「戦士のポーズ」「猫のポーズ」「三角のポーズ」といった日本語のポーズ名は、動きのイメージが湧きやすく、参加者にも馴染みやすいです。サンスクリット語の響きに比べて、構えずに受け取ってもらえるのが大きな利点だと感じています。
目的や効果を丁寧に伝える
ポーズの名前を伝える前に、「この動きは背中を伸ばしてリラックスするためのものです」「肩こりの緩和に効果的ですよ」など、「何のために行うのか」を伝えることに重きを置いています。これだけで、参加者の皆さんの理解度が格段に高まります。
動きそのものを具体的にリードする
「両手を上に伸ばして、ゆっくり体を横に倒していきましょう」といったように、動きを言葉で細かくガイドすることで、ポーズの名前を知らなくても自然にそのポーズがとれるようになります。名前を伝えるよりも、行動への具体的な誘導が大切だと考えています。
雰囲気ではなく、身体で感じてもらうことを重視する
僕は、ポーズの名前や複雑な理論よりも、「呼吸がしやすくなった」「腰が軽くなった」「なんだかスッキリした」といった、ご自身の身体を通して得られる実感を大切にしてもらいたいと考えています。ヨガは、頭で理解するだけでなく、身体を通して「感じる」ものだからです。
こうした工夫をすることで、ポーズ名に過度に頼らなくても、僕の伝えたい意図がしっかりと伝わるクラスができています。結果として、参加者の方々から「分かりやすい!」「安心して動けた!」といったフィードバックをいただくことも多く、それが僕にとっての何よりの喜びであり、日々の指導のモチベーションになっています。
まとめ
ヨガのポーズ名、特にサンスクリット語での名称をすべて完璧に覚えていなくても、まったく問題ありません。日本語で分かりやすく、そして目の前の人に寄り添って伝えられれば、それで十分にヨガの良さは伝わるというのが、私の長年の指導経験を通しての実感です。
もちろん、ヨガの歴史や伝統を学ぶ上で、サンスクリット語の知識を知ることは意味がありますし、それを尊重する姿勢も非常に大切です。ただ、その知識を「どう使うか」は、あなたが指導する場の目的や、参加者のニーズに合わせて柔軟に選べばいいのです。
大切なのは、「何を知っているか」よりも、「どう伝えるか」です。目の前の人が安心して身体を動かし、心から心地よさを感じられること。それこそが、ヨガの本質であり、私たちが目指すべきゴールではないでしょうか。




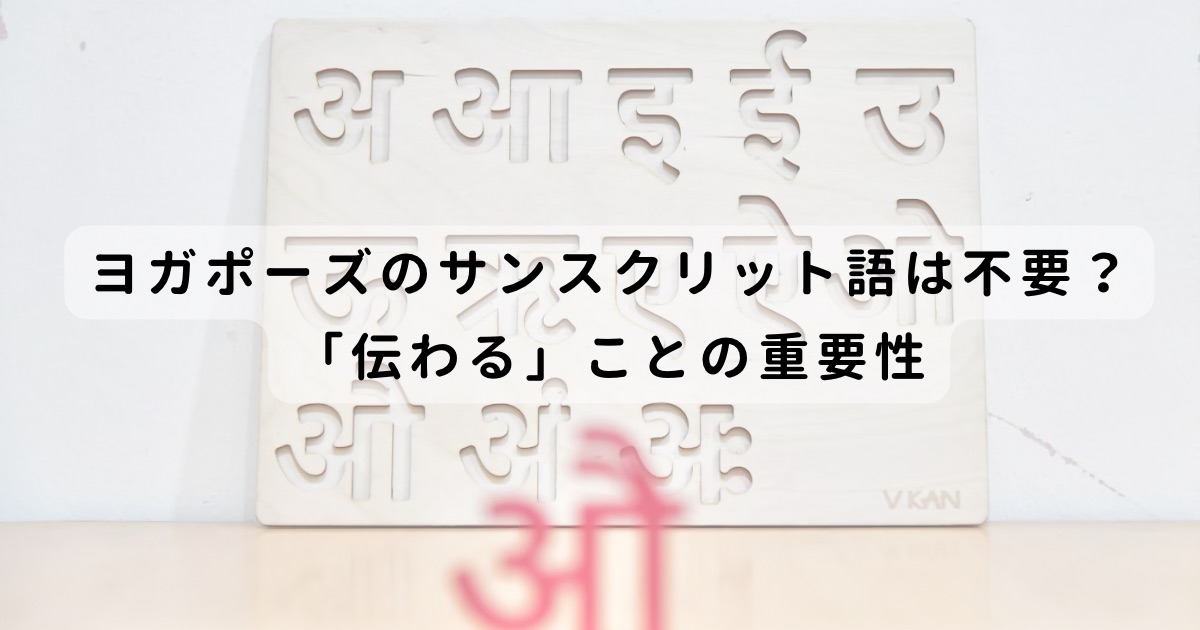

コメント